
なぜ今「シニア × 格安SIM」が注目されているのか?
高齢者のスマホ利用率が急上昇している背景とは
総務省のデータによると、60代〜80代のスマートフォン利用率は年々増加傾向にあります。
特に70代のスマホ保有率はコロナ禍を境に大きく伸び、現在では60%以上がスマホを日常的に使用しています。
これは「連絡手段としてのLINEの普及」「孫との写真・ビデオ通話の需要」「キャッシュレス決済の対応」が主な要因です。
ガラケーからの乗り換えを検討する中で、「料金が安く、使いやすいスマホを選びたい」というニーズが急増しています。
この流れに合わせ、各社がシニア向けに使いやすさや料金面で配慮された格安SIMを展開するようになってきました。
使い方はシンプルでOK。電話とLINEが使えれば十分な人が大半
シニア層のスマホ利用目的を見てみると、実に8割以上が「通話」「LINEのやり取り」「写真閲覧・撮影」にとどまっています。
動画視聴やアプリの多用は少なく、通信容量は1〜3GBで十分なケースがほとんどです。
つまり、複雑な機能や高速通信は必ずしも必要ではありません。
それに対応する格安SIMプランを選ぶことで、月額料金を1,000円以下に抑えることも可能です。
「スマホは難しい」と敬遠していた高齢者でも、必要最低限の機能に絞れば快適に使えるようになります。
格安SIMの進化とともに“サポート体制”も変わってきた
一昔前の格安SIMは「安いけどサポートがない」という印象が強く、シニア層にとってはハードルが高いものでした。
しかし近年では電話窓口・訪問設定・リモートサポートといった体制が整備され、初心者でも安心して契約できるサービスが増加しています。
また、シニア向けのサポート専用端末(ボタンが大きく操作しやすい)や「自動設定済みSIM」が送られてくる会社もあり、設定の手間を省けるようになりました。
「格安SIM=サポートがない」は、もはや過去の話と言えるでしょう。
家族がサポートしやすい「格安SIM × シニア」の利点
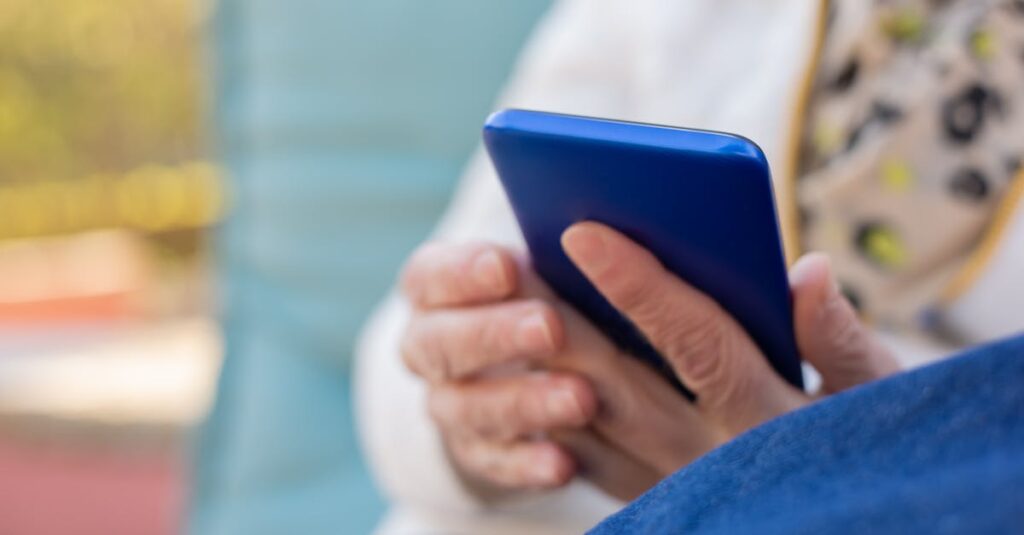
高齢の親にスマホを持たせる際、多くのケースで契約や初期設定を子供世代が代行しています。
格安SIMであれば、WEB上で契約手続きや名義変更、プラン変更が簡単に行えるため、遠方からでも支援しやすいのが魅力です。
また、SIMと端末をセットで送れるサービスもあるため、「親が店舗に行かなくてもスマホが使える」状況を整えることが可能です。
格安SIMは単に料金が安いだけでなく、親子の距離を超えたサポート連携を築けるツールにもなっています。
「スマホは難しい」「どの会社がいいのかわからない」
そんな不安を抱えていた方も、ここまで読んでいただけたなら、もう大丈夫です。
シニアが格安SIMで後悔しないための5つのチェックポイント
1. 本当に「電話だけでいい」のか?使用スタイルの見極めが最優先
「電話とLINEができれば十分」と思っていても、いざ使い始めると天気アプリやカメラ、調べものなど意外と使いたくなるものです。
そのため、契約前にスマホの使用目的を丁寧に整理しておくことがとても重要です。
動画視聴はしないけど、写真の送受信や地図アプリを使うなら、データ容量は最低でも3GB程度必要です。
逆に、本当に通話中心ならデータ通信は最小限でOKなので、音声通話が充実している格安SIMを選びましょう。
2. 「サポート付き」の格安SIMを選ぶのが安心
格安SIMには、料金が安い代わりにサポートがないプランも多く存在します。
スマホに不慣れなシニア世代には、「電話サポート」や「遠隔操作サポート」がある事業者を選ぶことが大切です。
中には「初期設定済みスマホ」をセットで販売してくれる会社や、訪問設定サービスを用意しているところもあります。
料金だけで判断せず、「使い始めてから困らない」ことを重視して選びましょう。
3. 使っているスマホ端末との相性を必ず確認
現在使っているスマホに格安SIMを差して使いたい場合、「SIMフリー端末」かどうかを確認しましょう。
キャリアで購入したスマホはSIMロックがかかっていることがあり、格安SIMが使えない可能性があります。
また、対応バンド(電波の種類)が異なると、通信が安定しない場合もあります。
初心者の方には、スマホ端末とSIMカードがセットになった「格安スマホセット」がおすすめです。
4. 契約名義と支払い方法にも注意が必要
シニアの親にスマホを持たせる場合、契約名義を「親名義」にするか「子供の名義」にするかで迷うことがあります。
親が支払いに慣れていない場合やクレジットカードを持っていない場合は、子供名義で契約した方がスムーズです。
また、支払い方法に「口座振替」や「デビットカード」が使えるかも確認しておきましょう。
支払いでトラブルが起こると、使いたいときに使えないというストレスにつながります。
5. 乗り換え前に準備しておくべき“事前確認リスト”

格安SIMへ乗り換える前に、以下のポイントを事前に確認しておくことで、トラブルを回避できます。
・現在のスマホがSIMフリーかどうか
・電話番号をそのまま使いたい場合はMNP予約番号の取得
・格安SIMが対応しているスマホ機種かどうか
・契約時に必要な本人確認書類の準備
これらを準備しておくことで、契約から利用開始までが非常にスムーズになります。
特にシニアが絡む場合は、事前準備の有無が安心感を大きく左右します。
「スマホは難しい」「どの会社がいいのかわからない」
そんな不安を抱えていた方も、ここまで読んでいただけたなら、もう大丈夫です。
2025年版|シニアに優しい格安SIM会社7選【タイプ別で紹介】
1. 通話重視タイプ:OCNモバイルONE|電話中心でも安心のかけ放題プラン
OCNモバイルONEは、通話メインでスマホを使うシニアに特におすすめの格安SIMです。
月額1,000円台から始められる音声SIMに、10分かけ放題や完全かけ放題オプションをつけることができます。
NTT系列のサービスという安心感もあり、通話品質が高く、通話中心の使い方をする方には非常に向いています。
また、店舗ではなく電話サポートが充実しており、初期設定で不安な方も安心です。
2. サポート重視タイプ:イオンモバイル|店舗で相談できる格安SIM
「スマホの操作や設定を誰かに相談したい」というシニアの方には、イオンモバイルが最適です。
全国のイオン店舗で契約や設定サポートを受けられるため、対面でのサポートを希望する方にとって大きなメリットとなります。
料金も月額858円〜と非常にリーズナブルで、必要な容量だけ選べる細かなプラン設計が特徴です。
また、家族と一緒に契約してデータをシェアする「シェアプラン」も利用可能です。
3. スマホセットで楽々タイプ:楽天モバイル|機種も一緒に届いてすぐ使える
楽天モバイルは、スマホ端末とSIMがセットで届き、初期設定もほぼ不要な「すぐに使える格安スマホ」が魅力です。
シニアが自分でスマホを設定するのが不安な場合でも、家族がオンラインで代行しやすい仕組みが整っています。
料金は月額0円〜3,278円(使った分だけ)とシンプルで、楽天ポイントが貯まりやすいのも嬉しいポイント。
通信エリアや通話品質も年々改善されており、都市部では特に快適に使えます。
4. 操作簡単スマホとセット:UQモバイル|かんたんスマホとの相性抜群
UQモバイルは、京セラの「かんたんスマホ」シリーズとのセット販売で人気の高いサービスです。
ボタンが大きく、ホーム画面がシンプルなスマホと、安定した通信環境をセットで提供しています。
au回線を使っているため通信品質も高く、初めてのスマホデビューにもぴったりです。
また、全国のUQスポットで対面サポートが受けられるのも大きな安心材料です。
5. 電話とLINEだけでOK派:HISモバイル|最安クラスの音声通話プラン
とにかくコストを抑えたい方には、HISモバイルの「かけ放題プラン」がおすすめです。
基本料金は月額550円〜と非常に安く、5分かけ放題付きでも月額1,180円前後に抑えられます。
LINE通話やメール程度の軽い通信なら、データ容量1GB〜で十分対応可能です。
サポート面では電話相談が可能で、公式サイトにもわかりやすい操作ガイドが豊富に用意されています。
6. 家族でまとめて安く:IIJmio|複数回線を一括管理できるお得プラン
IIJmioは、家族で複数回線を使いたい方にとって、料金面・管理面の両方で優れた格安SIMです。
月額850円〜という低価格で音声通話SIMを利用でき、通話定額やデータシェア機能も充実。
子供が親の回線を一括で管理できる「ファミリーシェア」などもあり、遠隔からのサポートにも最適です。
通信品質も高く、コストと安心感のバランスが取れた選択肢といえるでしょう。
7. 60歳以上限定割引:mineo|シニア割引がある唯一の格安SIM
mineoは、60歳以上を対象とした「シニア割」プランを提供している数少ない格安SIMです。
通話定額・サポート・端末セットなど、シニアが不安に感じる要素に手厚く対応しています。
また、初心者向けに「ゆっくり設定サポート」などの有料オプションも用意されており、安心して使い始めることができます。
データ容量や通話スタイルに合わせて、柔軟にプランを選べるのも大きな魅力です。

高齢の親にスマホと格安SIMを持たせるときに子供がすべき準備
1. 「いきなり渡さない」が鉄則。段階的な導入がカギ
高齢の親にスマホを持たせる際、もっとも大切なのは「いきなり渡さないこと」です。
ガラケーからスマホに乗り換える場合、操作方法や用語が大きく変わるため、戸惑うことが多くなります。
まずは家族が使い方を実演し、「電話」「LINE」「カメラ」など必要な機能だけを絞って紹介しましょう。
1週間ほど使いながら慣れてもらう時間を設けることで、拒否感を減らすことができます。
2. スマホとSIMの初期設定は子供が代行しておく
スマホに不慣れなシニアの場合、初期設定やAPN設定は難易度が高く、ストレスになりがちです。
そのため、端末が届いた時点で子供がSIMの挿入、初期設定、LINEのインストールなどを代行しておくことをおすすめします。
初期画面を「電話」「LINE」「写真」だけにカスタマイズすることで、操作ミスのリスクも減らせます。
その後、親に渡す前に一度一緒に使ってみる時間を持つと、より安心して利用を始められます。
3. トラブル時の連絡手段と対処法を事前に共有
スマホの使い方に慣れていないうちは、「困ったときに誰にどう連絡すればよいか」が大きな不安要素になります。
家族間で「この番号にかければいい」「このLINEで相談してね」とあらかじめ共有しておきましょう。
また、トラブルが起きたときは「再起動」「電源オフ→オン」「SIM抜き差し」など、基本的な対処法を紙などに書いて渡しておくのも効果的です。
不安を感じた瞬間に「すぐ相談できる」と思える状態を作っておくことが安心感につながります。
4. 遠方の親をリモートでサポートする便利ツールの活用
遠方に住む高齢の親にスマホを持たせる場合、「リモートで操作をサポートできる環境」を用意しておくと非常に便利です。
例えば「Google リモートデスクトップ」や「TeamViewer」などをインストールしておけば、トラブル時に自宅から親のスマホを一時的に操作できます。
また、「LINE通話で画面を映してもらいながら操作を教える」という方法も簡単で効果的です。
日常的なやり取りの中に少しずつサポートを組み込むことで、親も徐々にスマホに慣れていきます。

これで安心!格安SIMに乗り換える手順と注意点
1. MNP予約からSIM到着までの基本の流れ
現在の電話番号をそのまま使いたい場合、「MNP(番号ポータビリティ)」の手続きが必要です。
まず、現在契約している携帯会社のサイトまたは店舗で「MNP予約番号」を取得します。
次に、乗り換え先の格安SIM会社のWebサイトで、取得した番号を使って申し込みを行います。
申し込み完了後、数日でSIMカードが自宅に届きます。
2. SIMの挿入と初期設定はここに注意
SIMカードが届いたら、スマホに挿入し、必要に応じて「APN設定(ネットワーク接続の設定)」を行います。
設定方法は格安SIM会社から送られてくるマニュアルに沿って進めるのが基本です。
端末によっては設定不要な場合もありますが、不安な方は電話サポートや動画マニュアルを活用すると安心です。
また、SIMを挿す際はスマホの電源を必ず切っておきましょう。
3. 開通後にすぐ確認すべきチェックポイント
SIMを挿して設定を完了したら、次の3点を必ずチェックしましょう。
・電話の発着信ができるか
・モバイルデータ通信(4G/LTEなど)が使えるか
・LINEやメールが正常に使えるか
特に、通話ができないまま放置すると、緊急時に困るリスクがあります。
設定後は、家族と試しに通話やLINEを送り合いながら、正常に動作しているかを確認してください。
4. トラブル時にやってはいけないNG行動とは?
SIMカードがうまく動作しない場合、多くの人が慌ててスマホを初期化してしまうことがあります。
これは非常に危険で、大切な写真や連絡先がすべて消えてしまう可能性があります。
まずは冷静に、SIMの再挿入、再起動、設定の見直しを行い、それでも解決しない場合は公式サポートに相談しましょう。
「自己判断で操作しない」が、トラブルを最小限に抑える最大のポイントです。

「スマホは難しい」「どの会社がいいのかわからない」
そんな不安を抱えていた方も、ここまで読んでいただけたなら、もう大丈夫です。